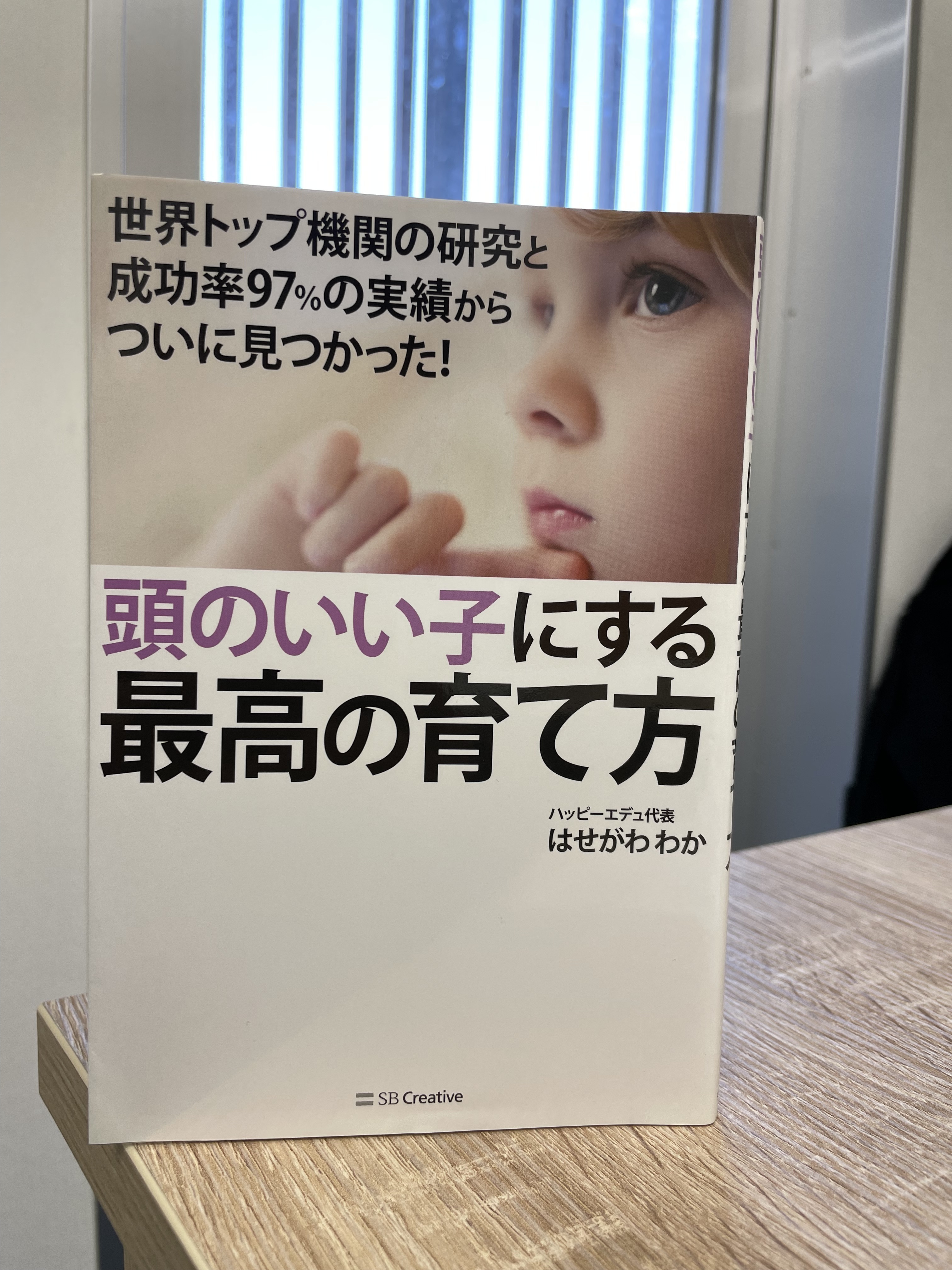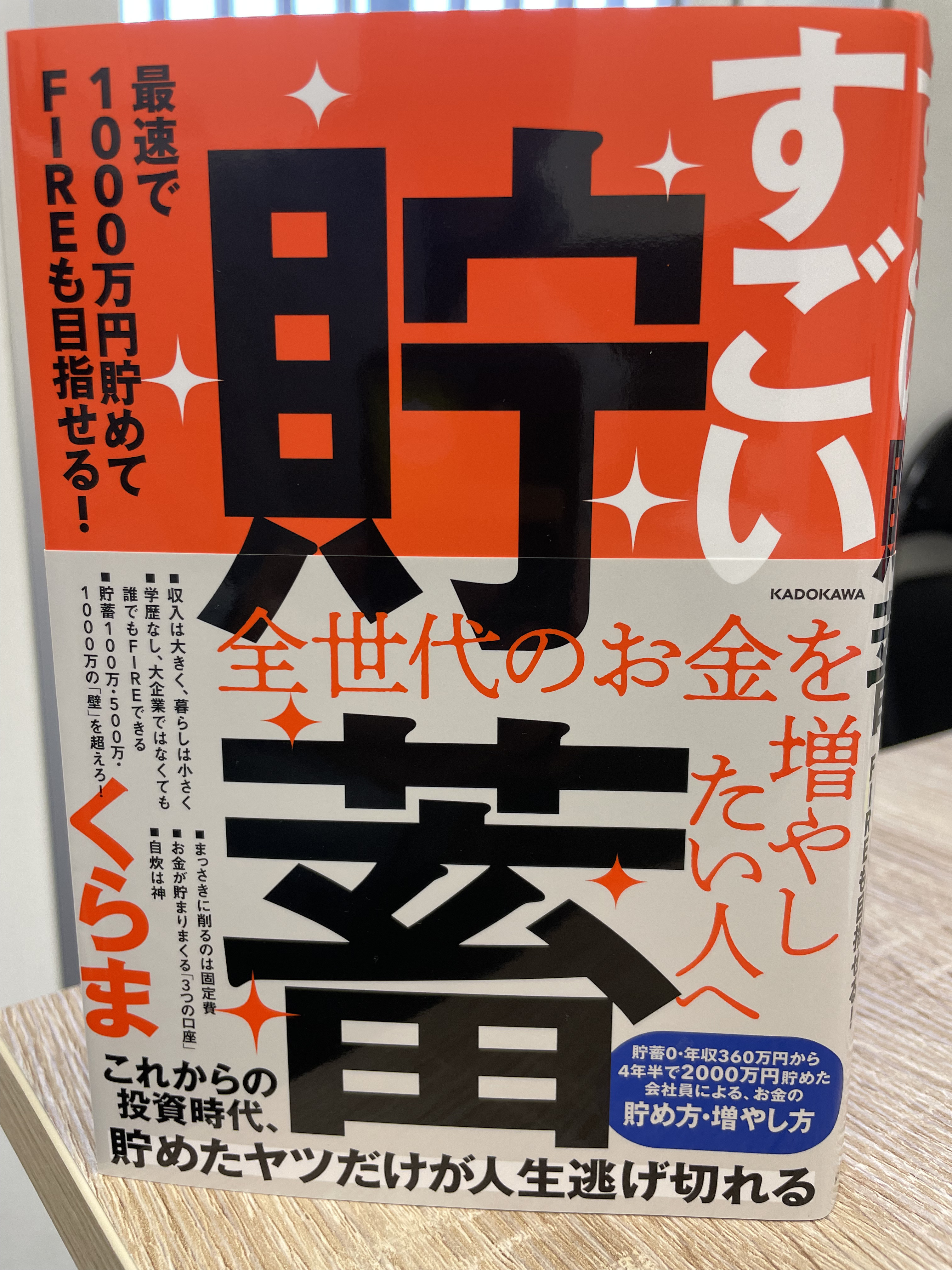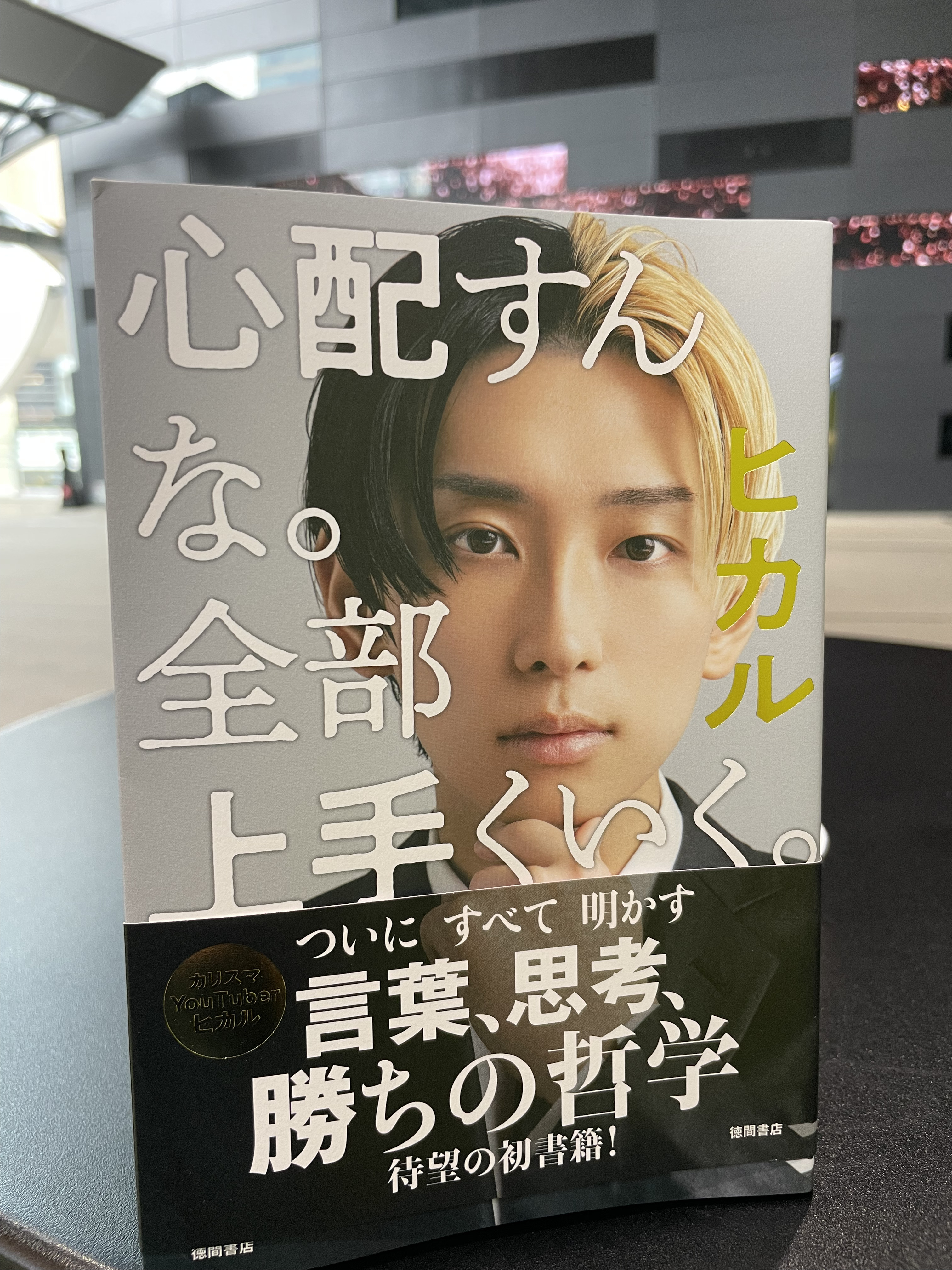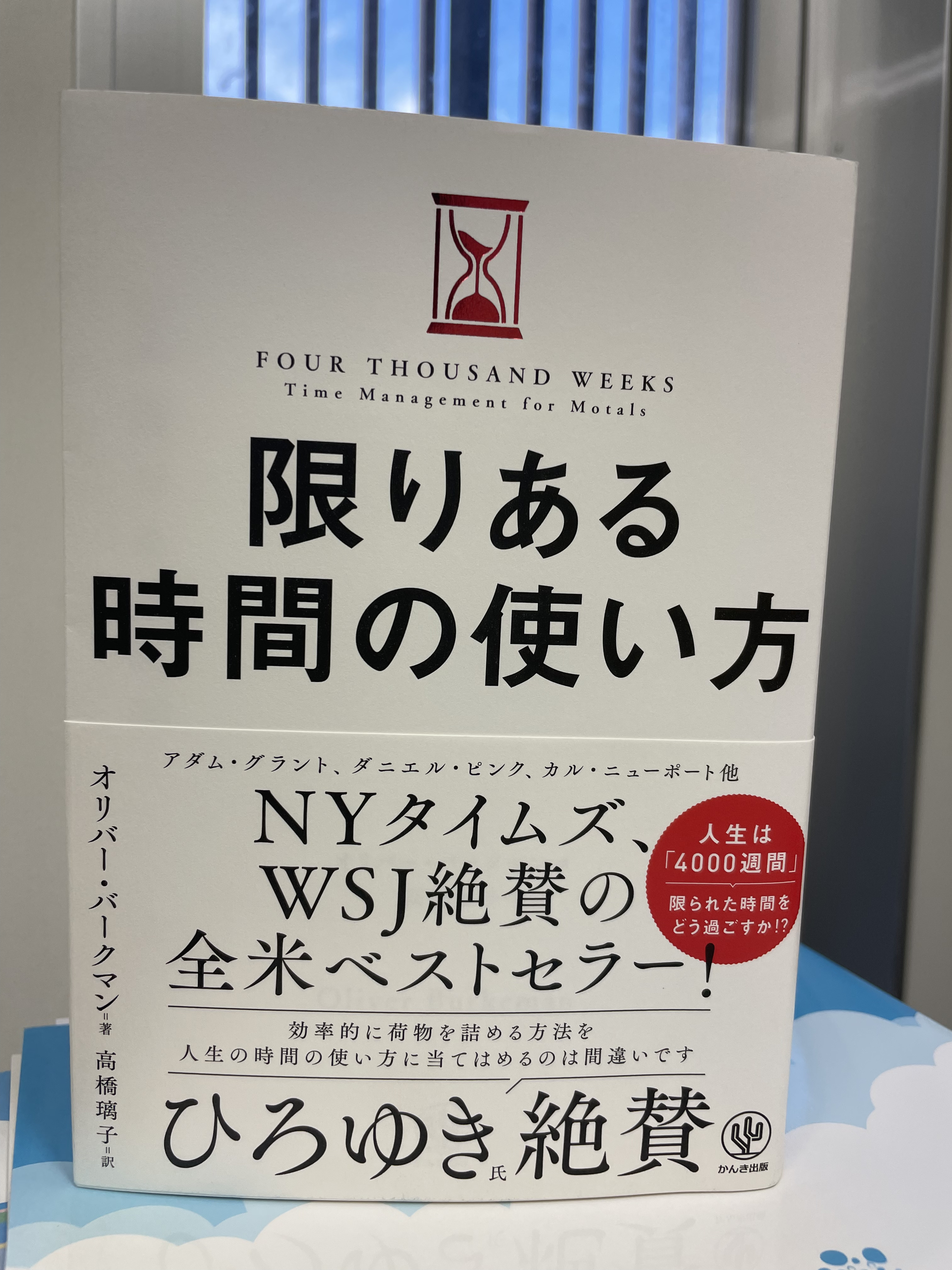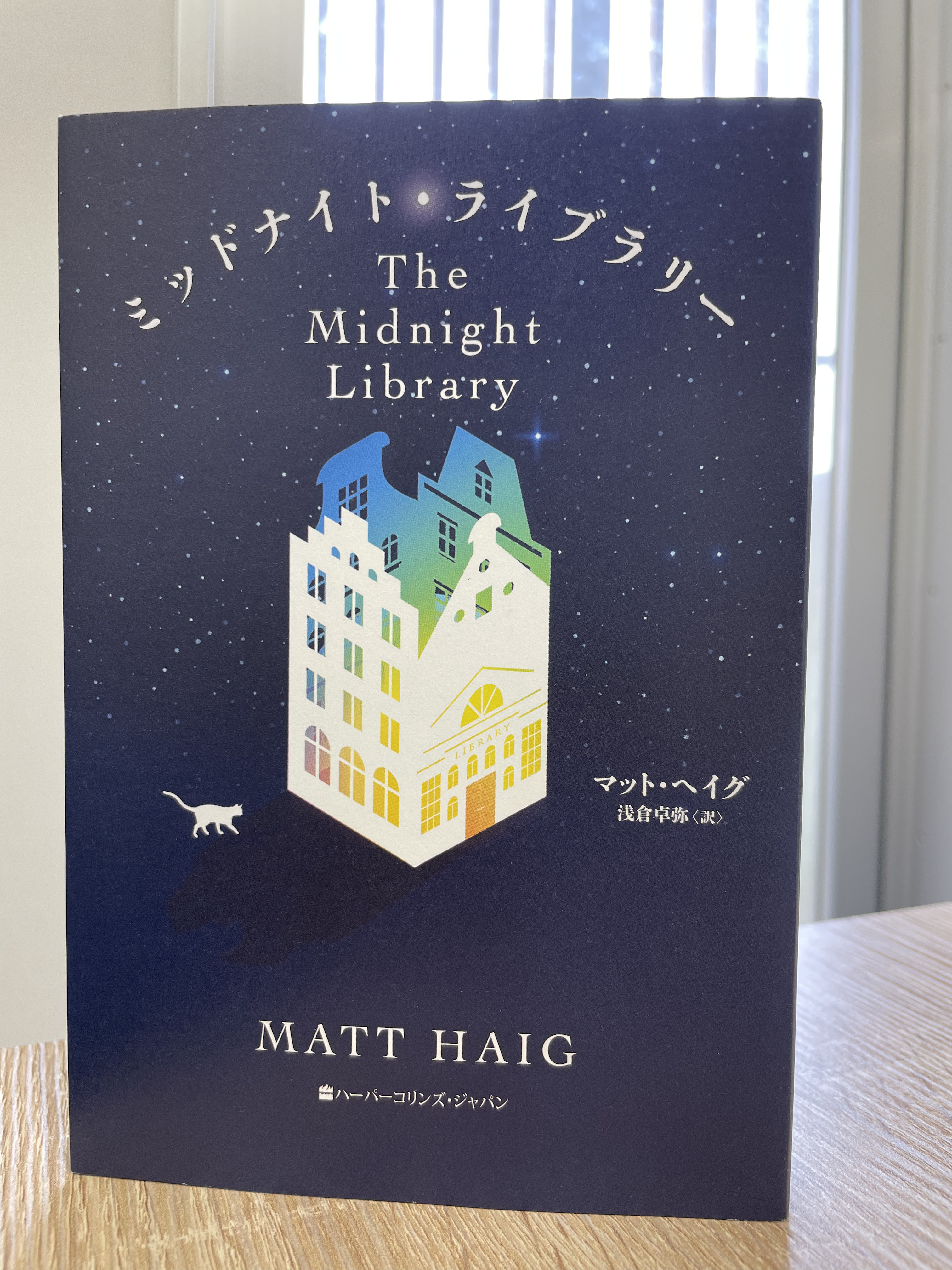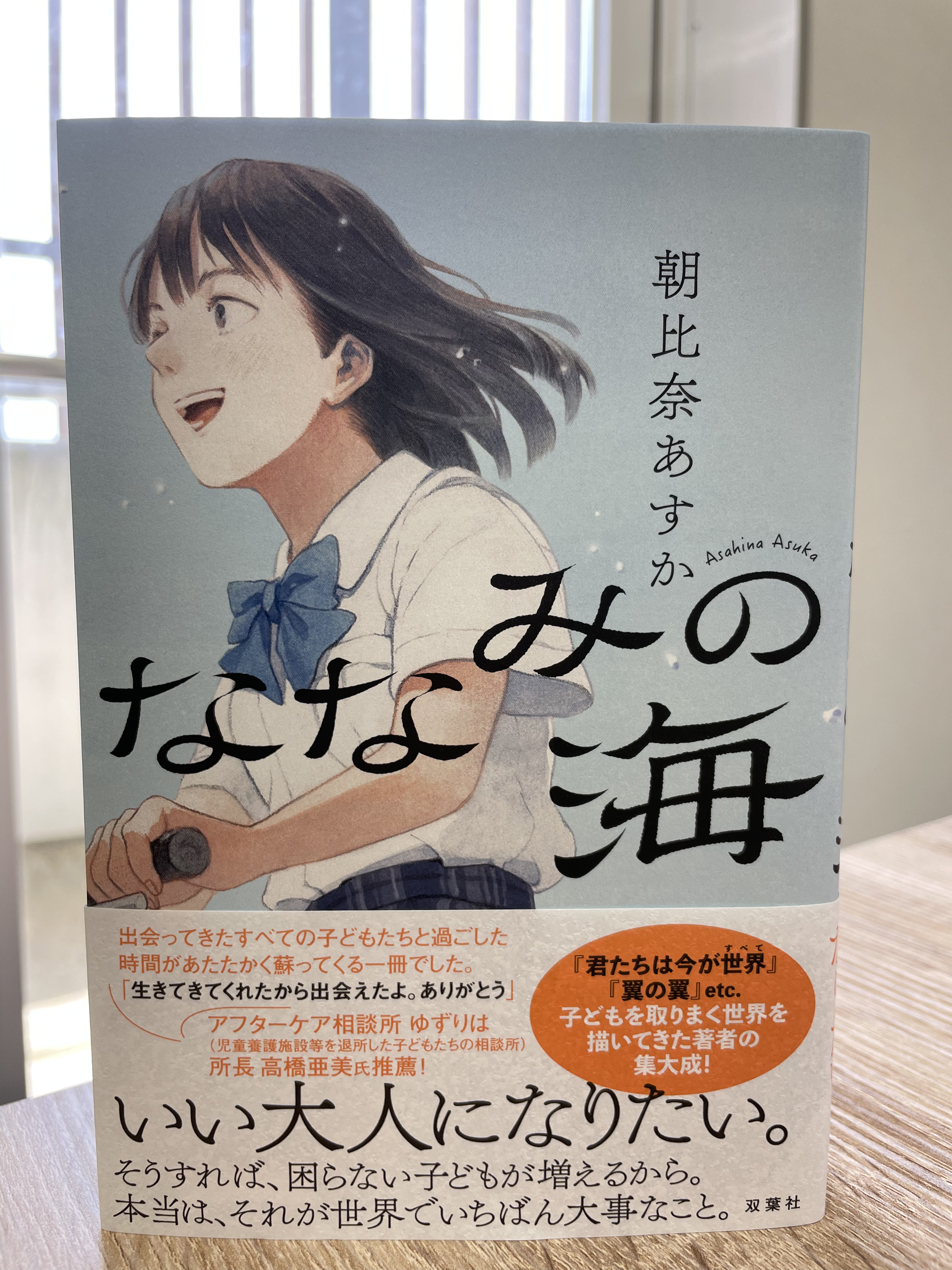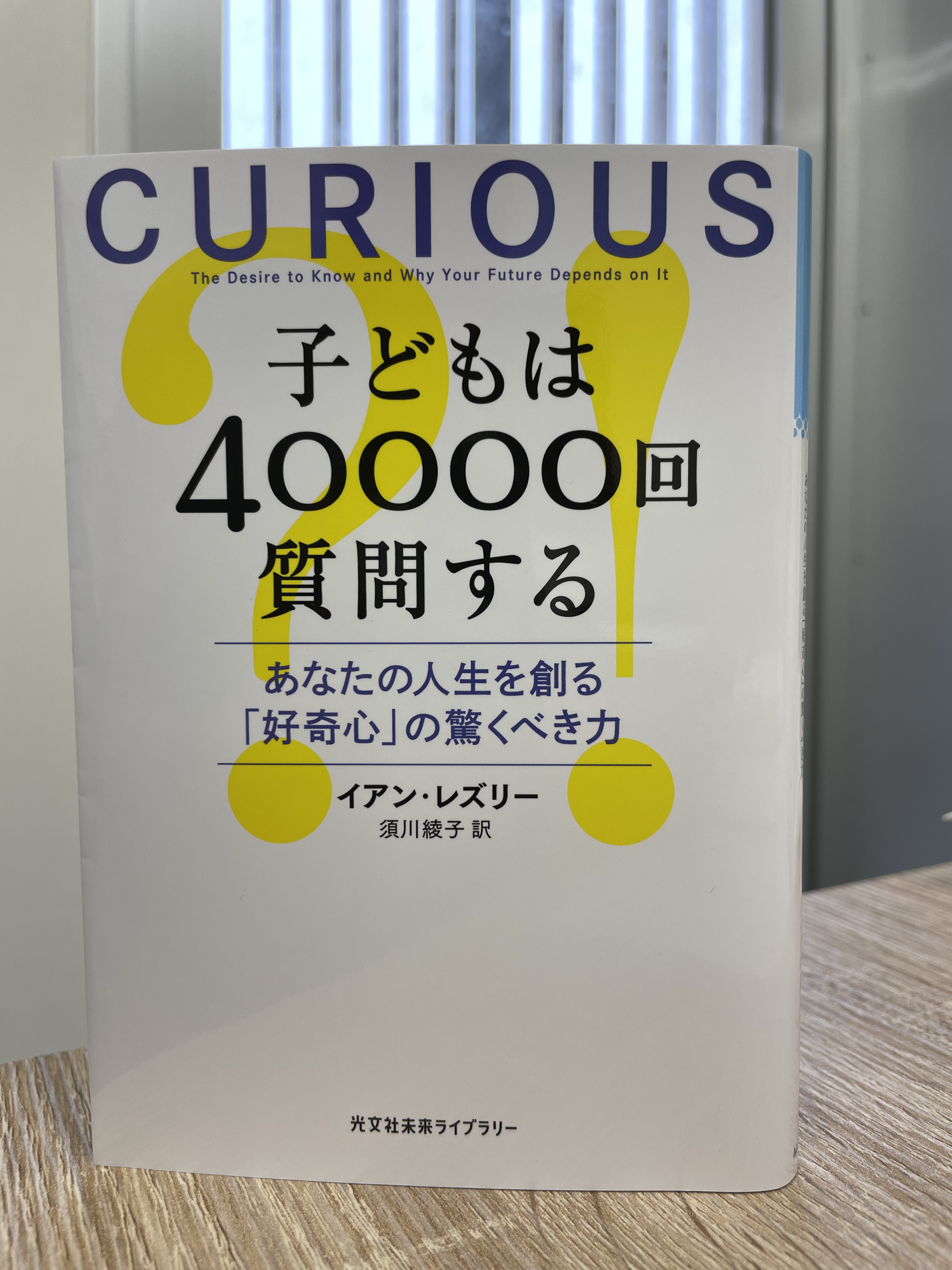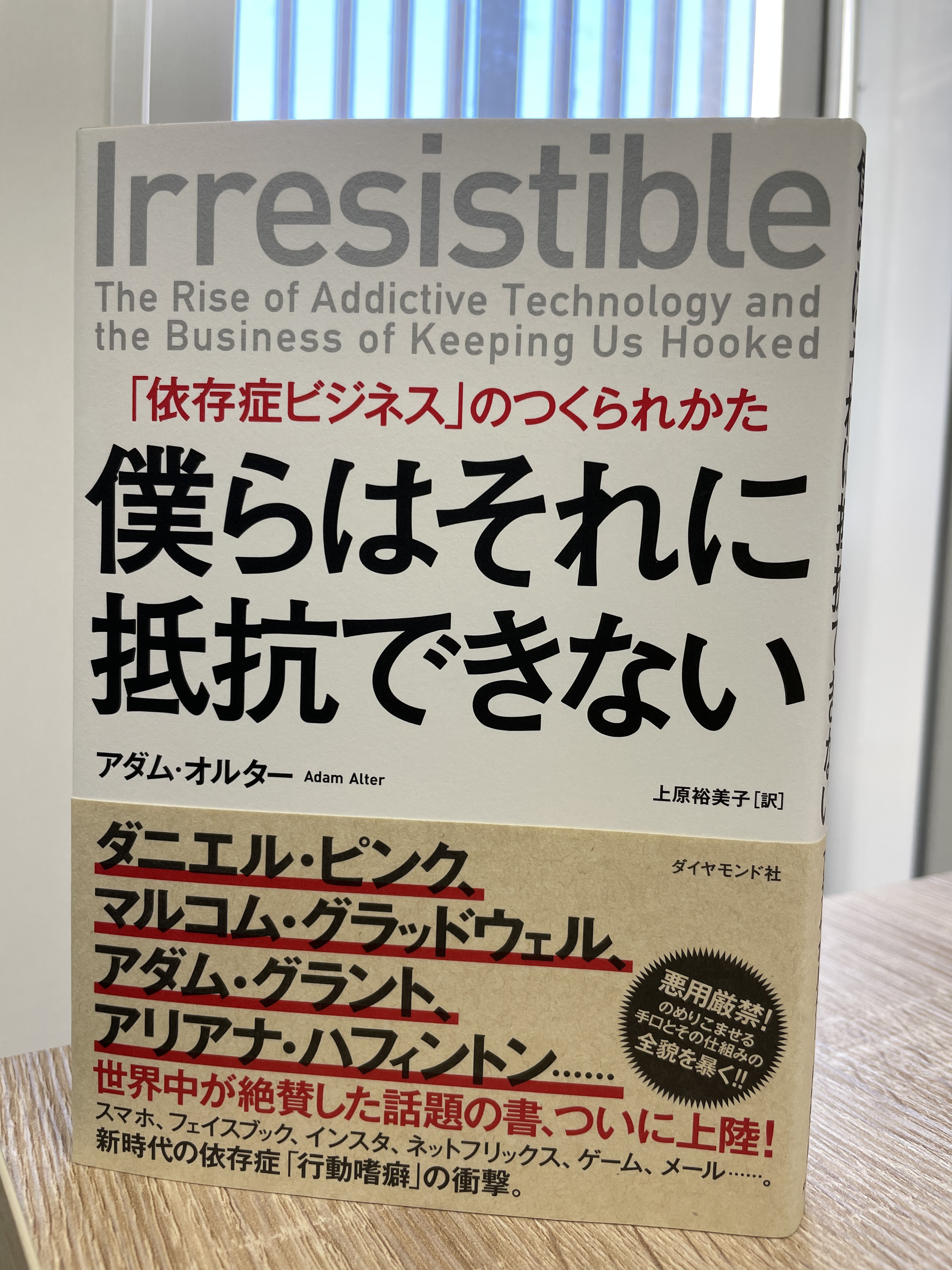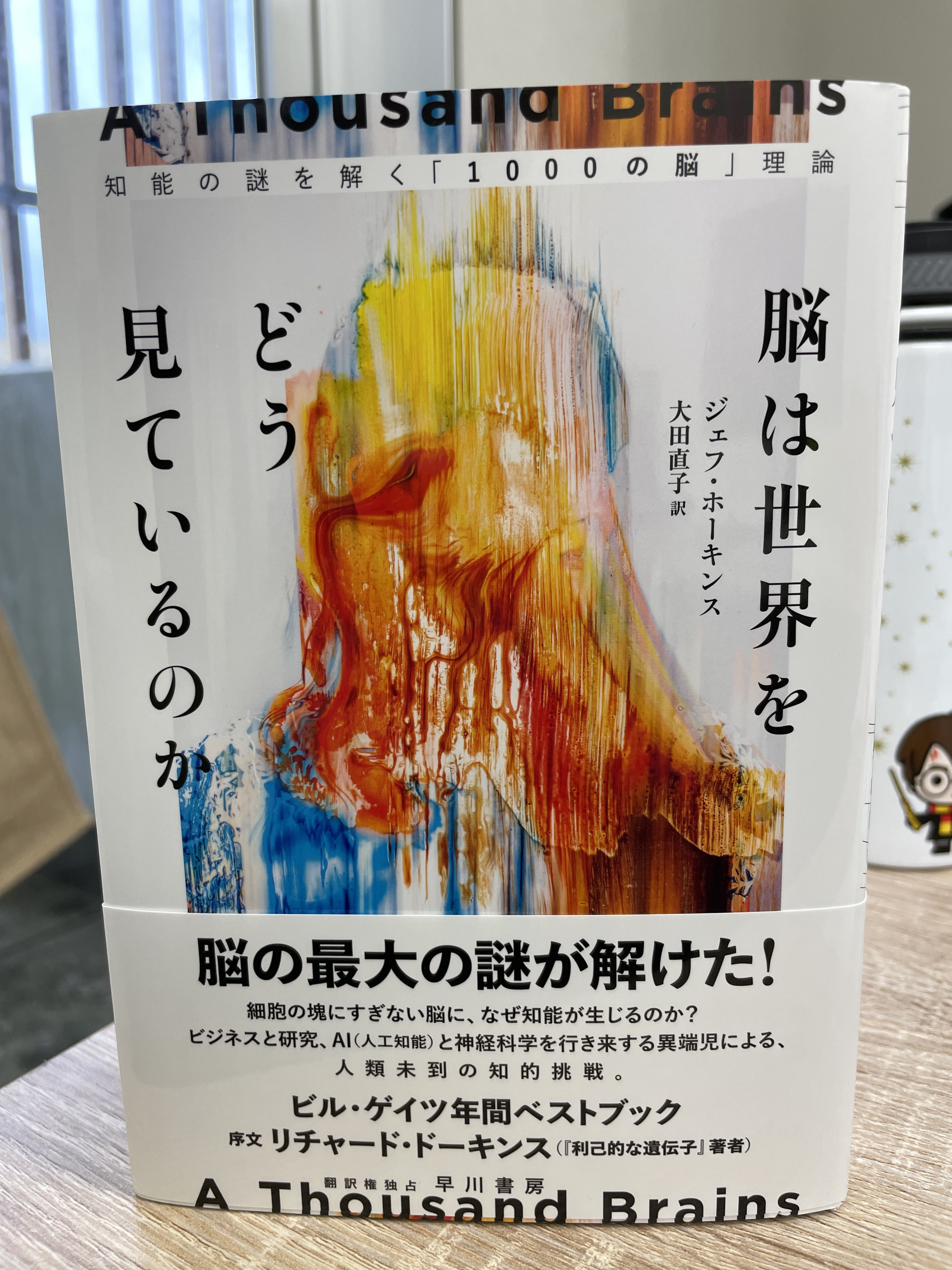[勉強]勉強法の極意
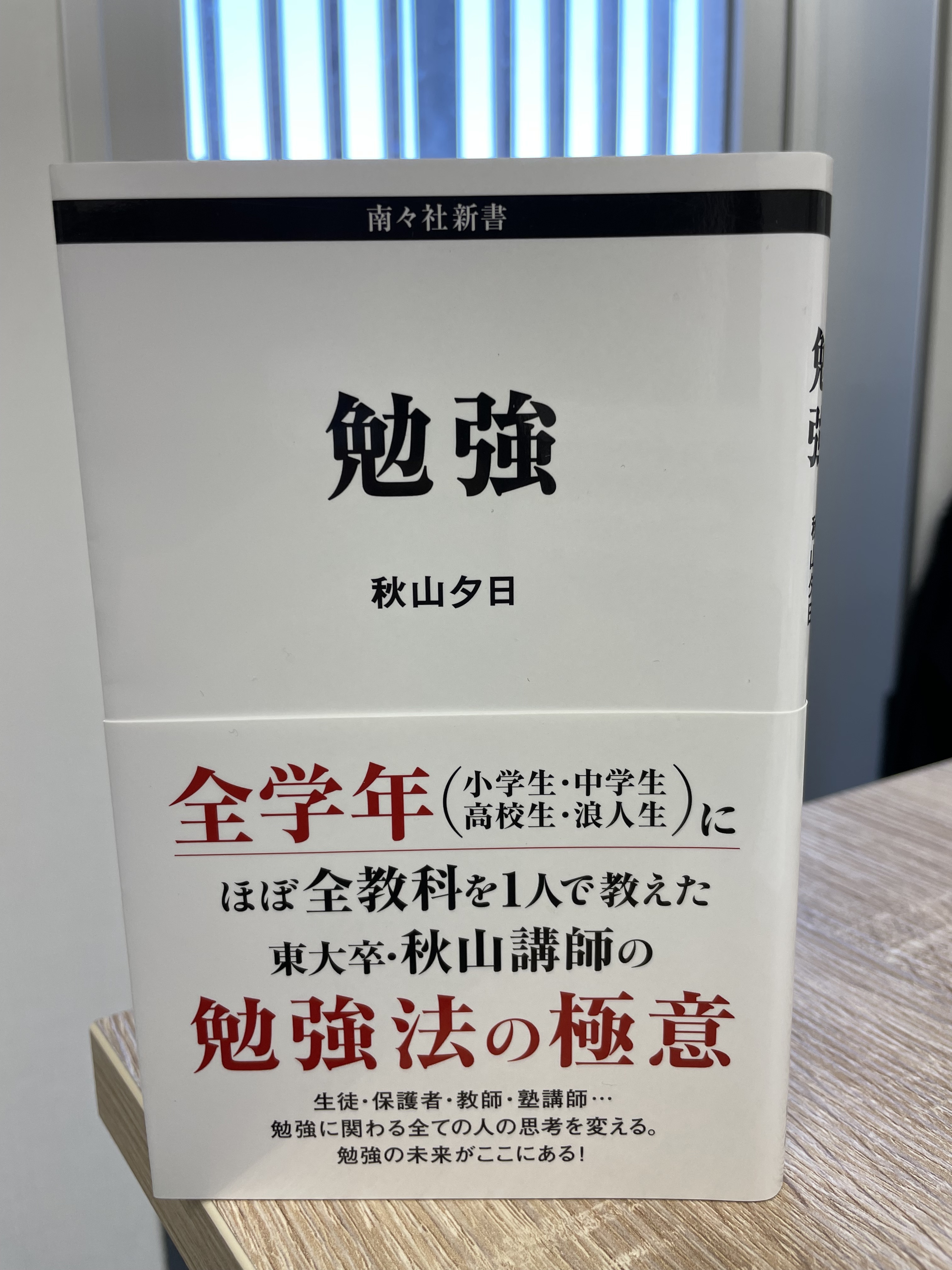
今回は集団、個別、家庭教師、映像授業...あらゆる形態の受験指導を経験した秋山氏による著書「勉強」より、勉強の極意とは何なのかを考えていきたいと思います。
本作は勉強に関する指導論のみならず、生徒・保護者対応、進路指導まで踏み込んだ運営面に関するアドバイスも満載で、受験生のみならず塾講師が読んでもためになる一冊です。
まず、小学生や中学生など、精神面が完成されていない学年に向けてできることは、「生徒の勉強そのものを褒める」ということです。目標とする点数や学習量に対して、どの程度学習できたか、習慣化できたか、その姿勢を評価する必要性を述べています。ある程度自発的に学習できる高校生、大学受験生と異なり、小中学生に対する指導はこうした学習に対する向き合い方、取り組み程度、課題をこなすといった観点から見守るとよいそうです。そして、学年が上がるにつれ、学習の技術的側面や演習量の確保といった次元へと指導スタイルを柔軟に変化させていきます。
勉強の具体的な極意について、たとえば文章題や応用問題への向き合い方があります。応用力が身につかないなどよく話題として出てきますが、その原因はもう少し手前の基礎・基本がしっかりできていないことにあると言います。「しっかり」できているとは、その問題を百発百中できるという意味です。大人が足し算や九九の掛け算を間違えないのと同程度の完成力が「しっかり」なのです。ここの見極めが甘いまま先に進んでしまうと、文章題が解けない、応用が利かない、イージーミスが多いなどという現象が出てくるのです。「しっかり」は英単語などの暗記モノにも言えることで、単語帳を覚えるのであれば、3周では少なすぎます。5周、10周と繰り返し目に通し、しばらくは忘れない程度になって初めて暗記したと言えるのです。
このように、勉強の極意はごく初歩的なところにあります。基礎・基本を「しっかり」行うことができていれば、その先の個別具体的な科目学習や演習は自ら主体的に進めることができるのです。そういう段階にある生徒は個別指導や映像授業、どんな指導形態でも成績を伸ばしていくことができるでしょう。逆もまた然りで、学習の基礎・基本が抜けた状態では一流のクラス授業、有名講師の映像指導を受けても活用しきれないということです。まずは上記の勉強の極意を身につけた上で、自身に合った指導形態を見つけてみてはいかがでしょうか。
2022年12月24日 13:05